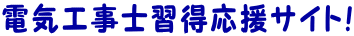
電線の引張り強さ - 電工超見習い
2015/12/23 (Wed) 21:05:07
はじめて投稿します。
現在、第二種電気工事士の筆記試験対策に取り組んでいますが
電気については全くのド素人です。
電線の接続要件の一つとして
「電線の引張り強さを20%以上減少させない」とあります。
(電気設備技術基準解釈第12条)
この文章を読んでも、このことは電気工事の現場でのイメージとして
どういうふうに解釈しておくべきことなのかさっぱり分かりません。
この「引張り強さ」という言葉はネット上でいろいろと調べてみると
以下のような説明がありました。
http://d-engineer.com/zairiki/anzenritu.html
もちろん電線を強く引張り続けると、いずれ電線はちぎれてしまうだろうし
単に電線・ケーブルといっても屋外と屋内では使う種類が違いますよね。
又、現在使用中の通称黒本と呼ばれる問題集には
「電線に張力の加わらない場合は、減少してもよい。
一般的に通常の屋内配線では、
電線を適宜固定すれば張力が加わることはない」
とあります。
「引張り強さを20%以上減少させない」という言葉を丸暗記すれば
それで済む話だと思いますが
意味やイメージを理解して試験に臨む方が断然有利だと思いますので
以下の質問にご解説いただきたい次第です。
よろしくお願いします。
(質問)
1、「引張り強さを20%以上減少させない」ということは
電線をどういう状態や状況で接続すればいいことになるのでしょうか?
2、「引張り強さを20%以上減少させない」ことに
背いて電線の接続をすると
なにかしら悪い結果や不都合な事、危ない事があるのでしょうか?
3、自分で調べていると、電気設備技術基準第7条に
「断線のおそれがないようにしなければならない」とありました。
この文章と「電線の引張り強さ」には何か関係がありますか?
4、「電線を適宜固定すれば張力が加わることはない」とは
具体的なイメージとして、どういう方法で電線を
施工することなのでしょうか?
Re: 電線の引張り強さ - とみやん URL
2015/12/25 (Fri) 21:12:33
こんにちは
書き込みありがとうございます
電線の引張強度との事ですが・・・
正直な話、工事をしていく中で特に意識はした事がないです・・・
引張強度という事で、電線同士の接続をした時に関係すると思います
一番関係しそうな感じなのが、がいし引き工事かと思います
がいし引き工事の結線では昔は巻きつけて、はんだを流し込む方法もありましたが、実際に工事をする時にはC形スリーブで接続すると思います
その時にスリーブの容量に合う様に減線する場合があります
その減線する時に20%以上は減線させない・・・といった感じでしょうか・・・
がいし引き工事に限らず、太い電線同士を接続する場合は減線してスリーブの容量に合わす場合があります
減線せずに通常の規定通りの接続をする場合は、引張強度を考えなくて良いと思われます
従って質問の返事としましては
質問1
電線の心線の本数のうち20%以上減線して接続しない
質問2
何かしらの張力がかかった場合にスリーブから抜けたり、接触不良になる可能性があるかと思います
質問3
電線の心線を減線することは、減線した分の電線の直径が小さくなり、本来の電線の強度から落ちてしまうので、張力がかかった場合に断線してしまう事があるかと思います
質問4
通常の配線や配管をして電線を収める場合は張力はほとんど加わらないと思います。がいし引き工事では、がいしにきちんと固定すれば電線に加わる張力は抑えられると思います。
また、ケーブルブッシング(ケーブルグランド)等も張力を抑える事が出来ると思います
確証があって述べている訳ではないので間違いなどがあればすみません
Re: 電線の引張り強さ - 電工超見習い
2015/12/30 (Wed) 16:08:48
こんにちは。詳しくご回答いただき有難うございます。
「減線」という言葉初めて知りました。
ご回答を何度も読み直しましたが、自分の理解が間違っていないかを
確かめる意味もあり、又、更に疑問が湧いたりしてますので
とりあえず以下にまた質問させていただきます。
質問
1)電線というものは通常の接続工事では
電線に張力を与えて施工するものではないが
引張られる状況で施工する場合は
引張り強度を考慮することになる。
2)現場での結線工事で「引張り強度を20%以上減少させない」ためには
電線の心線を20%以上減線しないようにすることに
よって対応することになる。
3)現在使用中テキスト等によれば
電線の心線は単線とより線の2種類あると
書かれています。
単線とより線では減線のやり方が異なるのでしょうか。
使用する工具等も含めて現場での減線という作業やり方がイメージできません。
以上ですが1)と2)は解釈が間違っているかどうかです。
3)については筆記試験でまず問われることはないと
思いますので、大まかにご説明いただければと思います。
よろしくお願いします。
Re: 電線の引張り強さ - とみやん URL
2016/01/02 (Sat) 11:14:40
こんにちは再度の書き込みありがとうございます
私も電線の減線についてネットで調べてみましたが、中々これといった解説がなされているページはありませんでした・・・
私も以前一緒に仕事をしていた上司から聞いていただけでの事で、それに根拠となる書物など有るかどうかは分かりません・・・
基本的に減線は、しないに越した事はないのが大前提での上でお願いいたします
しかし、実際の現場作業の時に、比較的太い電線複数本を同じに圧着する時に減線をすることがあります
私も全ての電気関係の法令を把握している訳ではなく、ただのいち現場職人なもので明確な判断が出来ないのは申し訳ございません
質問1
通常の電線同士の接続の場合は引張強度を考慮するより、接続点に張力が、かからない様に固定する事を考えます。それでも何かしらの影響で張力がかかりそうな時は、引張強度を考慮するべきだと思うのですが、通常の規定に沿ったスリーブの選定、圧着方法ならば引張強度に問題無いかと思います
質問2
これは、私の単純に考えた勝手な感覚です・・・減線に対する明確な規定が解らないので、やむおえず減線する場合でもそれ以上は減線しない方が良いかと思います
質問3
単線の場合は、心線が1本しかないので減線は出来ません。1本の線を削って細くする事は止めてください
より線の場合、心線が太さによって違いがありますが複数本寄り合わされています。例えば、22スケの場合は2mmの単線が7本寄り合わさっています。その内の1本を切断する感じです
作業イメージですが、22スケと14スケのスリーブでの接続の時に38スケのPスリーブを使用するのですが、IV等はCVより同じスケアサイズでも実際の直径は太くなっています。IV同士で接続するときにスリーブに入れにくい場合があり、何とか入れたと思った時に1本だけスリーブに入らず出てしまうことが有ります。その時にニッパーではみ出た電線を切るという感じです
文章下手でうまく説明できなくてすみません・・・
色々書きましたが、超簡単に言いますと、電線の引張強度を考慮するより、接続点には張力がかからない様に考慮する
減線は法の解釈が不明なので、どうしようもない場合にこっそりと行うという感じでお願いいたします
電気設備技術基準等の法令を学ぶのも大切ですが、内線規程という本もありますのでそれも機会があれば読んでみると良いかと思います。私は読んだことは無いのですが、職場の上司とかはよく、内線規程にこういう風に書いてあるから大丈夫と言うてるのを聞きます
Re: 電線の引張り強さ - 電工超見習い
2016/01/09 (Sat) 16:16:58
こんにちは。ご回答ありがとうございます。
電線の接続についてテキストに書いてあることが
以前よりもよくイメージできるようになりました。